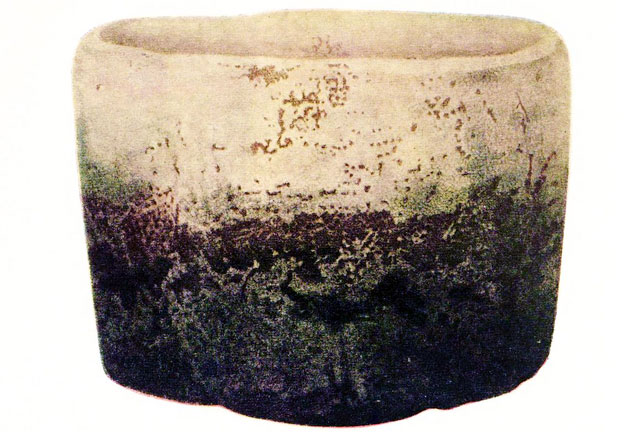「絵」の魅力を伝える額縁づくり
 栗原 大地氏 参照:https://www.athome-tobira.jp/story/181-kurihara-daichi.html
栗原 大地氏 参照:https://www.athome-tobira.jp/story/181-kurihara-daichi.html
栗原大地氏は1987年東京都出身です。美術鑑賞が好きだったこともあり、学生時代に額縁づくりに興味を持ち、額縁職人の道を選びました。修行の場は東京都の「東京の伝統工芸品」にも認定されている「東京額縁」の製造企業、富士製額。今回は地域の伝統工芸を守るため、研鑽を積む額縁職人栗原氏をご紹介します。
服飾デザイナー志望から額縁職人へ
 額縁の仕上げ工程。仕上げの色を塗り、箔押しを行う。 参照:https://www.fujiseigaku.com/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A3%BD%E9%A1%8D%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B/%E9%A1%8D%E7%B8%81%E8%A3%BD%E4%BD%9C/
額縁の仕上げ工程。仕上げの色を塗り、箔押しを行う。 参照:https://www.fujiseigaku.com/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A3%BD%E9%A1%8D%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B/%E9%A1%8D%E7%B8%81%E8%A3%BD%E4%BD%9C/
実はファッションに興味があり、服飾デザイナーを目指していたという栗原氏。学生時代にたまたま、祖父に現在職人として働く富士製額の工房を見学する機会があり、額縁づくりに興味を持ったといいます。
そのとき、栗原氏の頭の中では、もともと目指していたデザイナーとしての「人を飾る服」と、目の前の「絵を飾る額縁」という2つのことに共通点が見えたそうです。さらには、以前から絵画など美術鑑賞が趣味だったことも大きく影響し、一気に額縁職人への情熱が湧き上がり自分の進むべき道として選択をしたのでした。
東京の伝統工芸品「東京額縁」とは
 額縁を組み上げ。形状をつけた棹状の木材の両端を45°に切り出しボンドを塗り四隅から均等に圧力をかけ、組み上げる。
額縁を組み上げ。形状をつけた棹状の木材の両端を45°に切り出しボンドを塗り四隅から均等に圧力をかけ、組み上げる。
額縁の仕上げ工程。仕上げの色を塗り、箔押しを行う。 参照:https://www.fujiseigaku.com/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A3%BD%E9%A1%8D%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B/%E9%A1%8D%E7%B8%81%E8%A3%BD%E4%BD%9C/
明治以降、国内では洋画が台頭し額縁の需要も高まりを見せました。しかし、当時はまだ額縁の専門職は無く、指物、彫刻、塗装などの職人が分業で制作をしていました。
専門職の登場としては明治25年(1892年)、当時塗師であった長尾健吉がフランス帰りの洋画家山本芳翠の勧めで、芝愛宕町(現在の東京都港区愛宕一帯)に小工場を建てたのが最初だといわれており、これが現在の東京額縁の始まりだとも言われています。
現在の東京額縁の特徴は飾り型の模様にあり、アカンサスや月桂樹の花・葉、波、貝殻などに加えて、特有のものとして菊の花、葉、唐草などが使用されます。素材は、注文に合わせた種々の木材を使用、漆は天然漆、箔は金箔、銀箔を使用しています。
あくまで「絵」が主役を念頭に

額縁づくりに魅了された栗原氏は伝統工芸技術の継承者育成を目的とした、東京都荒川区の「荒川の匠育成事業」を利用して額縁づくりを見学した会社である富士製額で修行を積みます。平成29年からは同社に正式採用され、現在では額縁職人としてさまざまな作品をつくりだしています。
初めての作品が返品に
 さまざまな額の数々 参照:https://www.fujiseigaku.com/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A3%BD%E9%A1%8D%E3%81%AE%E8%A3%BD%E5%93%81/
さまざまな額の数々 参照:https://www.fujiseigaku.com/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A3%BD%E9%A1%8D%E3%81%AE%E8%A3%BD%E5%93%81/
「一番最初に額縁を全部一人で作ったのは3年目ぐらいの時ですね。師匠が、よく発注をいただける作家さんの額縁を『この先生の作品に合わせた額縁は、基礎が詰まってるからやってみろ』って任せてくれたのが最初です」と語る栗原氏。しかし、この初めての作品が作家さんから納得が得られずに返品されてしまいます。
作品は師匠にアドバイスを受けながらつくり直しましたが、その経験が「自分の作りたいものを作るだけでなく、お客様の要望に応えることが職人の仕事」ということに気づかせてくれたといいます。
それ以来、「額縁のせいで絵の魅力が伝わらなくなってしまうのは、作品を描いた作家さんにも大変失礼なことですから、『あくまでも絵が主役』という考えを常に念頭に置くようにしています」という自分の信念を確立したのです。
人を育て、人と出会うのが楽しい
 置くだけでまるで絵画。立体物専用の額縁FRAME FRAMEは、トレイ状に加工されたフレームと垂直に立ち上がったフレームからなる「2つのフレーム(額縁)によって構成されたアートベース」です。 参照:https://item.rakuten.co.jp/koikiya-tokyo/210/
置くだけでまるで絵画。立体物専用の額縁FRAME FRAMEは、トレイ状に加工されたフレームと垂直に立ち上がったフレームからなる「2つのフレーム(額縁)によって構成されたアートベース」です。 参照:https://item.rakuten.co.jp/koikiya-tokyo/210/
「美術館などで飾られるときは絵を描いた作家さんの名前は掲示されますが、額縁を作った職人の名前が載ることは絶対にありません。しかし、世界的に有名な画家の作品の一部になれるのはとても光栄なことです。そこが最大の魅力かな、と思います」と、語る栗原氏。
今でも美術館に足繁く通い、毎回新しい発見があると言います。額縁づくりはいくつもの工程や時間をかけての作業ですが、栗原氏の丁寧な仕事は師匠も一目を置くほど。主役ではないが、無くてはならない「額縁」という素晴らしい伝統工芸をこれからもひたむきに守っていってくれることでしょう。